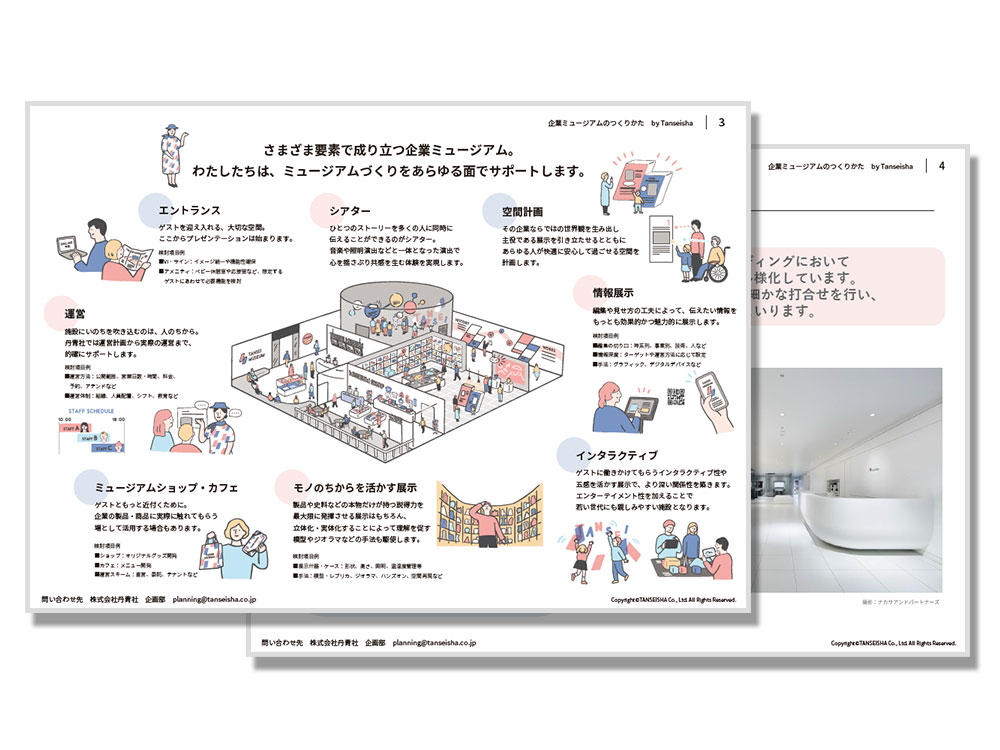企業ミュージアムにおいて
異質な存在である美術館が放つ輝き
Date: 2022.12.01

今回は、博物館経営、文化経営、産学連携教育をご専門に研究されている、
和光大学経済経営学部経営学科教授の平井宏典氏に、企業ミュージアムにおける「美術館」に焦点を絞りその可能性について、ご自身の研究を通じて考察頂きました。

平井宏典
1979年 神奈川県生まれ。2008年 東洋大学大学院経営学研究科博士後期課程修了 博士(経営学)
大学院在学時に東洋大学経営力創成研究センター(RCM)のリサーチアシスタントや民間企業のプロジェクト研究員等を務める。2009年に共栄大学国際経営学部専任講師、2013年に和光大学経済経営学部専任講師となり、現在に至る。
専門は、博物館経営、文化経営。ミュージアムの差別化戦略を中心的課題として「文化」と「経営」をキーワードに研究を進めている。また、大学ではProject Based Learning(PBL)型授業を担当し、実践的なビジネス学習プログラムの開発と実践に携わっている。

本コラムは、企業ミュージアムにおける「美術館」に焦点を絞って、その可能性について経営学の諸論と照らし合わせながら考察していく。学術的に企業博物館の定義において微妙な位置付けにある企業美術館は、その異質さ故の可能性を有していると考えられる。企業美術館は、企業にとってどのような可能性をもたらすのか、設置主体である企業と美術館の関係性から考えていく。
企業ミュージアムにおける美術館

2022年7月、「令和3年度社会教育調査」の中間報告が公表された。その中で、博物館数は過去最高の5,771館を記録している。1990年代初頭のバブル経済崩壊に端を発し、「失われた30年」と呼ばれた平成期の不況は、日本の博物館界にとっても経営面では「冬の時代」だった。令和となった今日も財政的には引き続き厳しい様相を呈しているが、博物館数は一貫して微増傾向にある。その背景には、博物館が社会における永続的な文化継承システムとして公的な位置付けにあるという守りの面と、近年では文化経済戦略や文化観光などにおいて(その良し悪しはともかく)博物館が「稼ぐ文化」の担い手のひとつであるという攻めの面の2つの要因があると考えられる。
日本は公立博物館が7割以上を占めており、3割以下の私立博物館の中には、学校法人による設立(大学博物館)や財団による設立などもあるため企業ミュージアムは数の上ではマイノリティと言える。そのマイノリティの中において、「企業美術館」という存在は、こと学術の世界では微妙な立ち位置にある。
企業ミュージアムは、博物館学・博物館研究の世界でも今後さらなる研究の蓄積が望まれる分野のひとつであり、その定義は明確であるとは言い難い。企業ミュージアムは、「企業が設立した博物館」であることは誰もが認めるところであるが、もうひとつの視点として「企業の事業に関係するもの」を掲げる研究者が多い。この視点によれば、ものづくりの企業が社会貢献の観点から美術館を設立して創業者の私的な美術コレクションを公開した場合、企業ミュージアムの定義から外れることになる。もちろん企業によっては美術品であっても企業の生業に関係することもあり、その場合は企業ミュージアムとみなすことができるが、その線引きは明確ではない。研究者によって、企業美術館を企業ミュージアムの定義に含める者もいれば、除外すると明言する者もいる。しかし、含める者であっても基本的には企業活動の延長線上に位置する場合を想定している。
実際に、企業ミュージアムの研究は、設立した企業の性質や活動と関連性の高い博物館が中心であり、企業美術館の存在はある種「異質なもの」と言える。しかし、企業美術館の存在感は決して薄いものではない。
拡張する企業ミュージアムの機能と役割
―開発・リニューアルの方向性
企業ミュージアムに関する機能と役割、リニューアルや開設の動向について株式会社丹青研究所上席研究員である石川が解説。

存在感を増す企業ミュージアム

東京の美術館を紹介する雑誌や書籍を見ると、根津美術館、東京ステーションギャラリー、三菱一号館美術館、森美術館、Bunkamura ザ・ミュージアム、出光美術館、五島美術館、サントリー美術館、山種美術館など、枚挙に暇がないほど企業美術館が取り上げられている。これらの企業美術館は、美術的な価値が高い資料を有するだけではなく、ユニークな建築や良好な立地、公立館にはみられないような良質な付帯施設・サービスを誇り、人気のデスティネーションというだけでなく当該地域の魅力向上に貢献しているケースも散見される。
企業ミュージアムのような私立館は、公立館と比較して、永続的な文化継承システムという博物館の本質的使命について懸念を抱かれることもある。しかし、展覧会を楽しむ利用者にとって設置主体の公私は無関係であり、公的な眼差しを持って質の高い博物館活動を展開している企業ミュージアムは少なくない。
2022年4月、改正博物館法が参院本会議で可決・成立し、従来は公的な性格を持つ主体に限定されていた登録博物館は、設置者による要件が撤廃、法人形態に関わらず登録できるようになった。この法改正は、博物館法の制定から70年が経過する中で、博物館を取り巻く環境が大きく変わり、法律の目的や事業の見直しを行い、社会に求められる今日的な博物館像を明確にするために行われたものである。
その改正の中で大きなポイントとなるのが登録制度の見直しであり、従来は法制度上「博物館」にカウントされなかった企業ミュージアムが登録館となり得ることになったのは、その存在感が増している証左であると言える。
CSRと企業美術館

これまで見てきたように、公立館が大多数を占める日本の博物館において、マイノリティである企業ミュージアムは、設置主体の公私の枠組みを越え、博物館の「底上げ」と「盛り立て」に寄与しうる存在として実質的にも制度的にも認められている現状にある。ここからは、企業ミュージアムという全体像から「企業美術館」に話の焦点を戻していく。
企業が美術館を設置・経営していくインセンティブはどこにあるのか。上述のように、企業ミュージアムは「企業が設立した博物館」であり、かつ「企業の生業に関係するもの」であるという見方が一般的である。企業博物館の場合、その資料や活動が設置主体である企業を基礎とすることから、社内外に対して直接的にポジティブな効果を期待することができる。
一方で、企業美術館は、「企業の生業に関係しない(もしくは関係が希薄な)」場合が多く、その資料や活動の結果が直接的に設置主体である企業のパフォーマンスに影響を与えるとは言い難い。企業博物館と比較して、直接的ではないにしろ、CSRの観点から間接的にポジティブな影響があるのではないかと想定することはできるだろう。SDGsを持ち出すまでもなく、企業も社会を構成する良き市民(企業市民)として、積極的にCSRに取り組むことは世界的な潮流である。
しかし、研究において積極的にCSRに取り組むことが企業のパフォーマンスを向上させるという明確な証拠を見出すことはできていない。フリーク・ヴァーミューレンは『ヤバい経営学(原題:Business Exposed, 2010)』の中で、「CSRに配慮する企業は、収益力のある企業であることが多い。(中略)好調な業績が、企業にもCSRを持たせるのだ」と指摘している。つまり、CSRと企業のパフォーマンス向上の相関は「鶏が先か、卵が先か」のようなものであると言える。
ただし、CSRが企業のパフォーマンスを悪化させるという証拠もない。ある研究では、不祥事などの逆風下においてはCSRの取り組み度合いが低い企業の株価は下落し、逆に高い企業の株価は大きく下がらなかったという結果がみられた(保険効果)。ある限定的な条件下ではCSRが企業にポジティブな影響を与えることもあるようだが、CSRが企業パフォーマンスにどのような影響があるのかについては、因果関係が複雑であり、「よく分からない」というのが現在のところの結論であると言える。

企業美術館の可能性

CSRは、短期的には企業のパフォーマンス向上に直接的な好影響を与えると言い切れないのであるならば、相対的に「企業の生業と関係ない」場合が多い企業美術館は、コスト要因になりかねない避けるべき存在なのだろうか。もう少し広い視野で企業美術館の可能性を深掘りしてみよう。
まず、簡単に思いつくのは保険効果である。上述した東京の美術館を紹介する雑誌や書籍で挙げられる企業美術館は、その資料や活動が一般的にも専門的にも高い評価を受けており、人気のデスティネーションと言える。設置主体である企業の提供する製品やサービスに関係の薄い人であっても、企業美術館を介してその企業にポジティブな感情を抱くことが期待できる。
また、企業美術館は本業との関係が希薄であるからこそ消費者と企業を結びつける新たな接点となりうる可能性もある。設置主体である企業のプロダクトの特質や消費行動の傾向などから本来は接する機会がほとんどない消費者とコミュニケーションを図る機会が生まれることで新たな可能性を探求することができるかもしれない。
さらに、企業美術館が取り扱う「美術」の本質的な価値とビジネスの関係性に目を向けてみよう。近年、ビジネスパーソンの間でも注目されている「アート的なものの考え方」は、今日の経営学で重視されている諸課題とつながりを見出すことができる。
美術(芸術)は、太古から現代に至るまで、常にその時代の技術革新と呼応しながら、新たなメディアを活用することで、表現の技法や形態を絶えず更新して、新たな価値観を生み出してきた。それは、提示された問題に対する答えを出すのではなく、問いを立てることそのものを探求する営為であるとも言える。企業を取り巻く経営環境が複雑化し、不確実性が高くなった現代社会では、正解は何かどころか、そもそも何が問題かすら判然としていない。このような状況下において、問い自体を探求することが重要になってきており、企業美術館の存在は社会に問いを投げかける姿勢を示すことにつながるのではないだろうか。
異質なものに取り組む意義

企業美術館は生業と関係がない(もしくは関係が希薄な)「異質な存在」であるからこそ、設置企業に対して多様性や新規性をもたらす可能性を秘めている。社会関係資本におけるネットワークの研究では、弱い結びつきの人間関係が情報の多様性・創造性を高める効果があることが立証されている。良好な関係にある友人とは、距離的にも心理的にも近く、趣味嗜好がある程度似ていることで、会う頻度が高く、親密さが増し、強い結びつきを構築することができる。一方で、仲の良かった大学時代の同級生が、卒業と同時に海外へ行ってしまい、滅多に会えない希薄な関係になってしまったとする。しかし、その同級生は海外という自分とは異なる環境にいるため、たまに連絡をとって話を聞くことが、思いがけない気づきや新たな発見につながる可能性がある。
このことは、どちらの方が優れているという問題ではなく、どちらもあった方が良いということであり、近年、イノベーション研究の領域で注目されている「両利きの経営」にも通じていると考えられる。企業は常に自社の事業領域について改善を繰り返し、より良いプロダクトを創出しようとする。それは自社のビジネス領域を「深化」させることであるが、その一方で視野狭窄に陥りやすく、逆にイノベーションを停滞させてしまう危険性を孕んでいる。そのような事態を避けるために企業は自社の事業領域にとらわれずに視野を広げる「探索」を行う必要性が指摘されている。設置主体である企業の生業が利き手であるならば、企業美術館という存在はビジネスという枠すらも超えて未知の世界を探索するもう一方の手としての役割を担うことができるのではないだろうか。
企業美術館は、美術という一見すると曖昧模糊としたものを扱い、企業に対して直接的なパフォーマンス向上を約束するものではなく、ビジネス的には不確実なものであるかもしれない。しかし、その不確実性は良い意味で企業に揺らぎを生み出す可能性がある。企業美術館の真の価値は、多様なステークホルダーを巻き込んで、その不確実性を企業経営に包含することになるのではないだろうか。